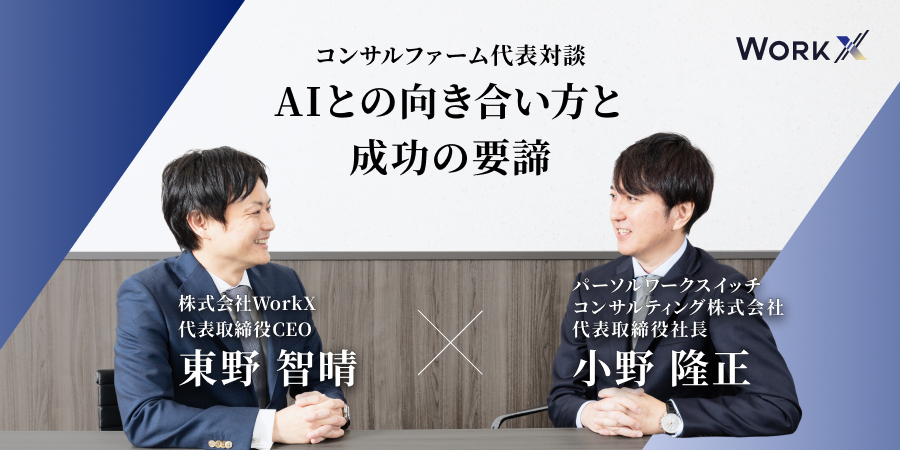
本記事のサマリ
この度WorkXは、パーソルワークススイッチコンサルティング株式会社(以下、パーソルワークスイッチコンサルティング)の代表小野氏をお招きし、WorkX代表の東野とAI領域についての対談を行いました。 (対談実施日:2025年10月15日)
プロフィール

小野 隆正氏
2004年に株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に入社し、外資系通信会社で常駐エンジニアなどを経験。その後、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社(現:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)にて、ITアウトソーシング部門統括部長やコンサルティング事業責任者、執行役員などを歴任。2023年10月、同社から分社化したパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社の代表取締役社長に就任し、現在に至る。

東野 智晴
WorkXとの関係性について
東野 本日はよろしくお願いいたします。まずは弊社WorkXとの具体的なお取り組みについて、改めてお聞かせいただけますでしょうか。
小野氏 よろしくお願いいたします。WorkXさんには、当社の多様なプロジェクトに専門人材をご紹介いただいています。特にAI領域や地域DX案件が多いですね。
東野 AI活用においてはインサイドセールス案件などで、弊社社員・フリーランスのプロフェッショナルがご協力させていただいております。
人とAIの「協働モデル」を目指す
東野 御社は今春「AIリーダーズ会議」に登壇されるなど、AIに非常に注力されていますが、どのようなお考えで取り組まれているのでしょうか?
小野氏 まず、パーソルグループとして、AIだけをやるというよりは、人とAIが共にはたらく「協働モデル」を世の中に伝えていきたいという考えがベースにあります。
“人が発想し、作業はAI”といった議論もありますが、何が正解かまだわかりません。
我々は、この協働モデルをどう管理するか、つまり「今は人がやるべき」「今はAIがやるべき」という役割分担を管理する手法や、ベースとなる考え方を提示していくべきだと考えています。
東野 その中で、具体的にどのようなAIプロジェクトに取り組まれていますか?
小野氏 大きく2つの方向性で取り組んでいます。
一つはワークフロー型のAIです。これは、元々我々が業務コンサルティングをやってきたので、業務フローを描き、AIがやる部分に生成AIなどを活用する取り組みです。
もう一つはエージェント型のAIです。コンサルティングの業務は定型作業ではなくワークフロー化が難しいため、コンサルタントのブレインワークを助けるAIをエージェント型で作ろうとしています。
東野 エージェント型は、通常のRAG(Retrieval-Augmented Generation)とは異なるアプローチなのでしょうか?
小野氏 はい、いわゆるRAGは大規模言語モデル(LLM)と社内データを組み合わせても「最大公約数」の成果、すなわち確率論的にもっともらしい回答にしかならないと考えています。
我々が目指しているのは、既存のデータやベストプラクティスを超えたアウトプットを生み出す、オープンエンドレスなモデルを構築することです。
東野 オープンエンドレス、面白いですね。
あとは、御社だとRPAなども得意なので、ワークフロー型はRPAと組み合わせたりと、課題に合わせたソリューションを提供していると捉えています。
小野氏 仰る通り、“生成AI”だけではないです。AIの研究者と話していても、生成AIはそこまで正確性が高くないよね、という話題になったりするので、生成AIに限定するのではなく、「ここで使う」と決めたらその業務に特化したシステムを作っていくことを考えています。
成功の要諦:PoCは大きくやるべき
東野 AI領域のプロジェクトを成功させるために、特に重要な要素は何とお考えでしょうか。
小野氏 これは難しいですが、どこでPoC(概念実証)をやるかという点をあげたいです。
日本では小さくPoCを積み重ねていくことが多いですが、AIにおいては「より大きく」「成功したらリターンが大きい」難易度の高いところから大きく始めてこそがPoCであると考えています。
東野 社会実験みたいなイメージでしょうか。
小野氏 そういうPoCにしないと、いくら小さいPoCを重ねても、誰も「これでいける」とはならないです。
東野 それは我々もよく目にします。いわゆる「PoC疲れ」「PoC死」ですね。
小野氏 特に日本ではそのように積み上げ方で考える会社が多いです。
海外のテクノロジーベンダーとも話しているのですが、やはり、より大きく、本当にリターンがあるところでこそPoCをやるべきだと。先ほど話したオープンエンドレスなテクノロジーと同じで、期待を超える成果、アウトプットを出していく必要があります。
東野 コンサルタントとしてのバリューも、計算できる範囲を超えないといけないですね。
小野氏 最近はそのように考えています。
AIと向き合う姿勢
東野 企業はどのような姿勢でAIに取り組むべきでしょうか?
小野氏 AIを「神格化しない」「コンピューティング(計算機)である」と心得る姿勢が必要です。世の中には「AIを入れたら人の仕事がなくなるのでは」といった無用な恐れによってブレーキがかかっているケースがあります。業務は減りますが、人間の仕事が完全になくなるわけではありません。
東野 やはりAIも実際使ってみると、精度含め限界を感じるので、業務は残りますよね。ITの歴史が示すように、技術が進んでも人がいらなくなったことはなく、むしろそれに関する仕事が増えてきました。
一方で、コンサルタント側はどのような姿勢でいるべきでしょうか。
小野氏 コンサルタントやエンジニアなどのプロフェッショナルは「AIで仕事が減るから困る」と考えるのではなく、「AIを使って、今やっている仕事の3倍、もしかしたら10倍のアウトプットが出せる」という考え方を持つべきです。
東野 同感です。ただ、こうなると育成をどうするか、というのも難しくなってきていると感じます。これは別の話なのでまた今度話させてください!
今後の展望:AGIからエッセンシャルワーカーまで
東野 今後のAI領域における御社の展望を教えていただけますか。
小野氏 短期的には、ワークフロー型とエージェント型を融合させ、エージェントが自律的に動くような世界観を作っていきたいです。
現在はホワイトカラー領域が中心ですが、中長期的にはフィジカルな領域、エッセンシャルワーカー領域、すなわち、工場、サプライチェーン、軽作業などの支援に踏み込んでいきたいと考えています。
東野 ハードルが高いなと思っているのが、ホワイトカラーはGPUを増やせばキャパシティが増えますが、フィジカル領域はロボットなどへのそれなりの投資が必要な点です。その投資が一般的に賃金の低いエッセンシャルワーカーの報酬に対して見合うようになるかも論点だと考えています。
小野氏 24時間はたらける、危ないところでもはたらけるなど付加価値も大きいため、前向きに考えています。
東野 文句も言わないですしね(笑)
WorkXへの期待:ピンポイントな経験者のアサイン
東野 最後に、現在弊社の社員・フリーランスによるAI領域のご支援は継続中ですが、WorkXへの今後の期待も伺えますか。
小野氏 AI領域はスピードが重要です。フリーランスの方々が持つ「知見の広さ」「経験の幅広さ」は、なかなか正社員のみのキャリアでは得難いものと思っています。
経験を積んだプロフェッショナルがいる分、プロジェクトの進行が非常に速くなりますので、ピンポイントな経験者の提供を引き続き期待しています。
東野 ありがとうございます。やはり知っている人がやると、速いですよね。
小野氏 今出ているAIだと、ちょっとしたことで劇的に精度が良くなったり、動かなかったものが突然動いたりなど、そういう世界なので特に経験の重要性を感じます。
東野 弊社として、適材適所でプロフェッショナルアサインし、効果的にプロジェクトを進めていくことを目指していますので、引き続きご支援させていただければ幸いです。
本日はどうもありがとうございました!
小野氏 ありがとうございました!

